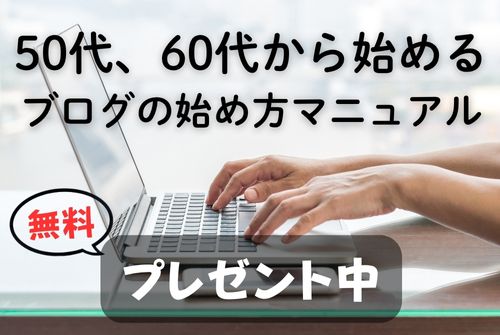老後不安から副業スタート…税金の壁に気づいた瞬間

なぜ今、副業ブログ・アフィリエイトが注目されているのか?
- 副業でブログやアフィリエイトを始める人が増えていますが、その理由は「老後の生活費が足りないかも」という現実的な不安が大きいです。
特に50代になると、年金や退職金だけで安心して暮らせるか不安に感じる人が多くなります。
副業ブログはパソコンとネット環境があれば自宅で始められ、スキルや経験がなくても収入につながりやすいのが特徴です。
また、コストも少なくて済むため、始めやすい点も人気の理由です。
たとえば、家計の支出を見直しても将来の医療費や生活費に不安が残るとき、「自分で少しでも収入を増やしたい」と考えるのが自然です。
ブログやアフィリエイトなら、会社勤めや家庭と両立しやすく、今までの人生経験や知識を記事に活かして収益化できます。
このように、老後への備えとして副業ブログは今の50代世代にぴったりの働き方といえます。
初めての収益で「税金」の存在に驚く人が多い理由
- ブログやアフィリエイトで初めてお金が振り込まれたとき、「これって税金どうなるの?」と戸惑う人がとても多いです。
普段の給料は会社が税金を引いてくれますが、副業の収入は自分で管理しなければなりません。
とくに副業収入が少額でも、一定額を超えると「確定申告」が必要です。
この仕組みを知らないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
たとえば、1万円や5万円といった収入が振り込まれたとき、最初は「お小遣い程度」と考えてしまいがちです。
でも後から「副業分の税金がかかる」「申告しないとペナルティがある」と知ってあわてる方が実際に多くいます。
副業ブログで収入があったら、早めに税金や確定申告の仕組みを確認しておくことが大切です。
所得20万円(給与者) / 所得48万円(非給与者)超で申告

サラリーマン(給与所得者)は「20万円」超で申告義務
- サラリーマンなど、会社からお給料をもらっている人は、副業の所得が20万円を超えたら必ず確定申告が必要です。
副業の収入には、「雑所得」や「事業所得」などがあります。
ここで大事なのは「所得」で考えること。
つまり、「副業で得たお金」から「経費」を引いた金額が20万円を超えたら申告が必要です。
お給料とは別に、アフィリエイトやブログ、投資、内職などの収入が対象になります。
たとえば、アフィリエイトで30万円の収入があっても、パソコン代や通信費など経費が15万円かかった場合、「所得」は15万円です。
この場合、申告は不要。
でも経費が5万円しかなかったら「所得」は25万円。20万円を超えるので確定申告しないといけません。
本業の収入とはしっかり区別して、副業分の「所得」が20万円を超えたら忘れずに申告しましょう。
専業主婦・年金生活者は「48万円」超が基準
- 専業主婦や年金生活の方は、年間の「所得」が48万円を超えると確定申告が必要になります。
「基礎控除」という制度で、誰でも年間48万円までは税金がかかりません。
でもこの金額を超えたら申告しなければいけません。
年金やパート収入も同じように、ブログやアフィリエイトの所得もカウントします。
たとえば、ブログで50万円の収入があって、経費が2万円だったら、所得は48万円。
ギリギリセーフ。
でも、経費が1万円しかなければ、所得は49万円。
1万円分だけ確定申告が必要になります。
専業主婦や年金生活者でも、所得48万円を超えたら申告が必要と覚えておきましょう。
所得=収入-経費! 勘違いしやすいポイント
- ブログやアフィリエイトの「所得」は、収入から経費を引いた金額。
ここを間違えると損してしまいます。
「収入」とは振り込まれたお金の総額ですが、「所得」はそこから必要な経費を差し引いた残りの金額です。
この経費には、サーバー代やドメイン代、書籍代、ネット回線など仕事に必要なお金が含まれます。
たとえば、年間収入が40万円でも経費が30万円かかったら、所得は10万円。
20万円や48万円の基準には届きません。
【経費の例一覧】
- サーバー代(ConoHa WINGなど)
- ドメイン代
- 専用の書籍・教材代
- ネット回線・Wi-Fi
- パソコンや周辺機器
- 作業場所の光熱費(自宅の一部を利用している場合)
「収入」と「所得」の違い、経費で差し引けるものをきちんと知って、正しく確定申告しましょう。
控除とは?経費って何?知らないと損する税金ルール
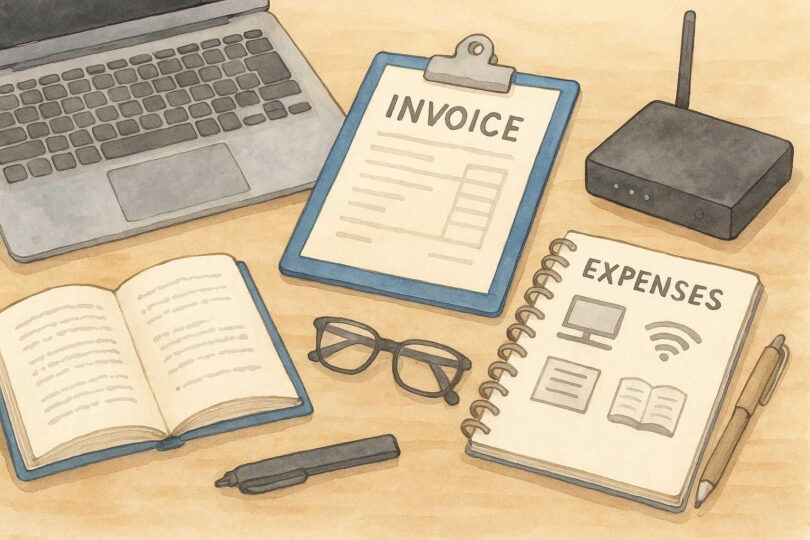
ブログ・アフィリエイトで使える経費の例
- ブログやアフィリエイトで収入を得るとき、「経費」をきちんと計上することで、課税される金額を大きく減らせます。
経費として認められるものは意外と多く、これを漏れなく申告すれば「所得」が少なくなり、結果的に節税につながります。
副業ブログでは、本業以上に経費管理がカギとなります。
たとえば、ConoHa WINGなどのサーバー代、独自ドメイン代、ブログ運営のための参考書(【ブログの参考書「ワントップ」】PR、ネット回線費用、WordPressテーマ(Lightning PR)などが経費にできます。
また、パソコンやマウス、作業部屋の電気代の一部なども該当する場合があります。
経費になるものをしっかりリストアップして申告すれば、その分手取りを増やせます。
副業ブログの所得区分は「雑所得」
- 副業でブログやアフィリエイト収入がある場合、多くの人は「雑所得」として申告します。
個人で行うブログ収入は「事業」として本格的に運営していない限り、「雑所得」扱いになります。
事業所得との大きな違いは、経費の幅や控除の内容、青色申告の対象かどうかなどに関係します。
たとえば、本業のかたわらブログで月数万円程度の収入がある場合や、専業主婦・年金生活者が趣味を活かして収益化している場合は「雑所得」になります。
事業所得と違い、赤字を他の所得と相殺できません。
ブログ収入はまず「雑所得」で申告、というのが一般的です。
青色申告・白色申告の違いとメリット
- 青色申告を選ぶと、最大65万円の控除が受けられるなどメリットが大きいですが、手間もかかります。
白色申告はシンプルで誰でもできる反面、特別な控除はありません。
一方、青色申告は事業所得や一定条件の雑所得で使え、帳簿付けや会計ソフトが必須です。
その分、節税効果は絶大です。
たとえば、青色申告なら「複式簿記」で記録することで65万円の控除。
会計ソフト(ラッコキーワードPRや、参考書ワントップPRなど)を使えば手間を大幅に減らせます。
副業でも長く続けて年収が増えるなら青色申告もおすすめです。
最初は白色申告、慣れてきたら青色申告にチャレンジするのが安心です。
実践例+節税テクニック(サーバー代、書籍など)

実例1:ブログ収入が少ないケース(申告不要)
- 副業ブログの収入が少ない場合は、確定申告が必要ないケースも多いです。
申告義務は「所得」で決まるので、収入が少なくても経費をしっかり引くと「基準額」を下回ることがあります。
経費を正しく差し引くことがポイントです。
たとえば、年間のブログ収入が18万円で、サーバー代やドメイン代など経費が3万円かかった場合、所得は15万円となり、サラリーマンなら20万円、専業主婦・年金生活者なら48万円の基準より下です。
この場合は申告不要となります。
「収入」ではなく「所得」で判断すること、経費を忘れずに計上することが大切です。
実例2:収入アップ後のケース(申告必要)
- 副業ブログの収入が増えて基準額を超えた場合、必ず確定申告が必要です。
収入が増えても、経費をきちんと差し引けば課税額を下げられますが、基準を超えたら申告を忘れずにしましょう。
基準額を超えているのに申告しないとペナルティのリスクがあります。
たとえば、年間のブログ収入が35万円で、経費が10万円の場合、所得は25万円です。
サラリーマンなら20万円を超えているので確定申告が必要です。
専業主婦・年金生活者でも48万円を超えた場合は申告必須です。
「経費を差し引いても基準額を超えたら必ず申告」、これが大原則です。
経費計上を徹底するコツと注意点
- 経費計上を徹底すれば、所得を少なくできるだけでなく、節税にもつながります。
経費は「領収書」や「レシート」をきちんと残しておくことが基本。
家計簿アプリやExcelを使えば管理もラクになり、税務調査にも対応しやすいです。
※Office系ツールのサブスクも、経費として計上しましょう。
たとえば、スマホでレシートを写真保存したり、Excelに日付・内容・金額を記録したり、家計簿アプリでまとめて管理する方法があります。
経費になるものはその都度記録しておくと、年末に慌てずに済みます。
「経費は証拠が命」。
領収書の保存とデータ管理を徹底しましょう。
サーバー・テーマ・ツールで経費計上できるもの
- ブログ運営にかかるサーバー代やテーマ代、ツールの利用料も全て経費計上できます。
ブログやアフィリエイトに必要な費用は「収入を得るために使ったお金」として経費にできます。
ConoHa WINGのサーバー代や、WordPressテーマLightningの購入費用、ラッコキーワードなど、実際に使っているツール代も対象です。
- サーバー代:ConoHa WING
- WordPressテーマ:Lightning
- キーワードツール:ラッコキーワード
- 参考書:「ワントップ」
使った分だけしっかり経費にして、節税効果を最大限にしましょう。
まとめ – 今すぐ使える申告ツール&チェックリスト
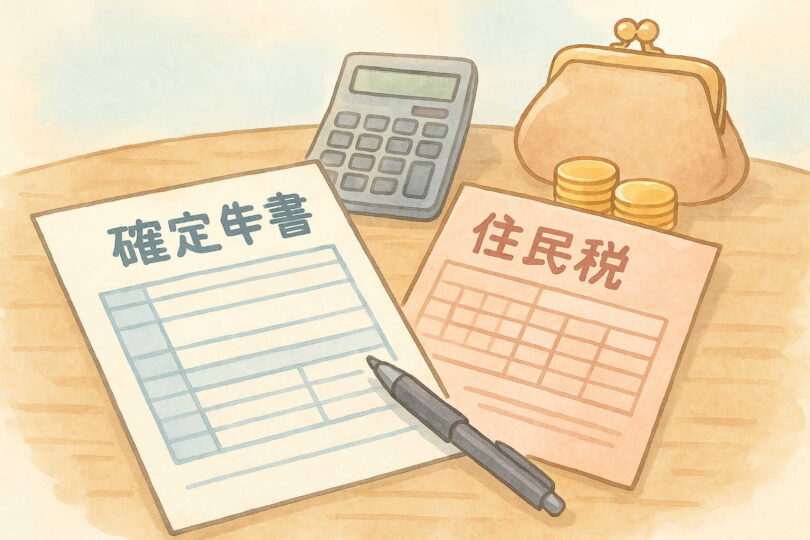
確定申告の手順をざっくり解説
- 確定申告の流れは思ったよりシンプルです。順番に進めれば誰でもできます。
「ややこしそう」と思われがちですが、やるべきことは大きく3つ。
収入と経費を集計し、申告書を作成して、e-Taxや郵送、窓口で提出すれば完了です。
- ステップ1:1年分の収入と経費をまとめる
領収書やレシート、通帳、振込記録を集めておきます。 - ステップ2:申告書を作成する
国税庁の「確定申告書作成コーナー」や会計ソフトを使えばかんたんに作成できます。 - ステップ3:提出方法を選ぶ
e-Tax(電子申告)・郵送・税務署窓口のいずれかで提出。e-Taxなら自宅から24時間提出可能です。
まずは「収入・経費の整理」から始めて、一つずつ進めていきましょう。
今からでも間に合う!50代がやるべき申告準備リスト
- 確定申告の準備は「今から」でも十分間に合います。
必要な書類やデータを早めにそろえておけば、申告期限が近づいても慌てずに済みます。
とくに副業ブログの場合、書類が少ないので管理もかんたんです。
- 1年分の収入記録(振込明細やレポートなど)
- 経費の領収書やレシート
- マイナンバーカード、身分証明書
- 銀行口座情報
- 税務署から届く書類(必要な場合)
申告準備は「やろう」と思った日から始めればOK。早めのチェックが安心につながります。
おすすめ会計ソフト・申告サポートサービス
- 初心者でも使いやすい会計ソフトや申告サポートを活用すれば、確定申告のハードルはぐっと下がります。
無料のものから有料まで、いろいろな選択肢があります。
自分に合うサービスを選ぶことで、ミスや手間を減らし、安心して申告ができます。
- 【無料】国税庁「確定申告書作成コーナー」
- 【有料】会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワードなど)
自分に合ったツールを使って、無理なく申告・節税しましょう。
FAQ
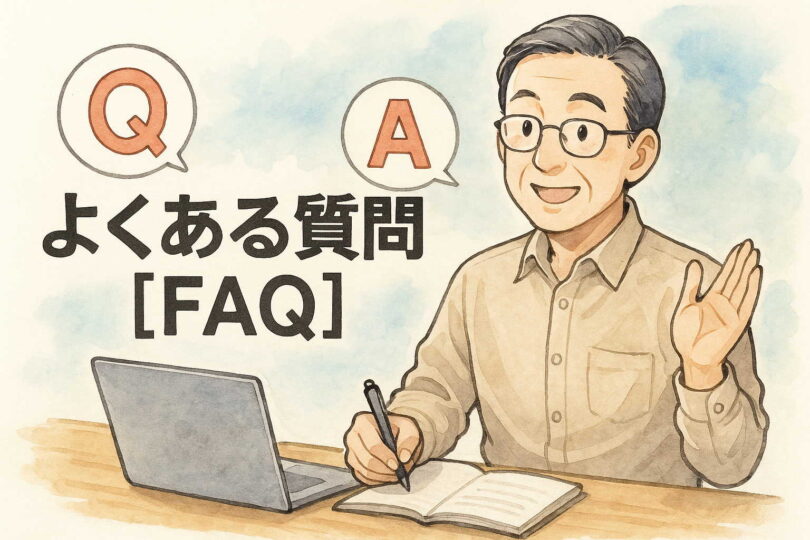
副業ブログが20万円以下でも住民税は?
- 副業ブログの所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要な場合があります。
所得税と住民税は別の計算になります。
所得税の申告義務がなくても、住民税の計算には副業の所得も含まれるため、自治体への申告が必要です。
また、住民税の「普通徴収」を選ぶことで、会社に副業がバレにくくなります。
たとえば副業所得が18万円の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告書を市区町村に提出すればOKです。
普通徴収を選択すれば、副業分だけ自分で納付できるので安心です。
「住民税は別」と覚えて、忘れずに自治体にも申告しましょう。
青色申告の65万円控除ってどうすれば使える?
- 青色申告の65万円控除を使うには、専用帳簿と開業届の提出が必要です。
青色申告で65万円控除を受けるには「複式簿記」で記帳し、「開業届」を税務署に提出していることが条件です。
帳簿付けが難しく感じますが、会計ソフトを使えば初心者でも可能です。
たとえば、ブログを事業レベルで運営する場合、開業届を出し、弥生やfreee、マネーフォワードなどの会計ソフトを使って複式簿記で帳簿をつければOKです。
手続きのサポートも多数あります。
「開業届と帳簿付け」さえ守れば、節税のチャンスが広がります。
副業バレが心配…普通徴収の申請とは?
- 副業が会社にバレたくない場合は、住民税の「普通徴収」を選ぶのが基本です。
普通徴収にすると、副業分の住民税は自分で納付できるので、会社の給料から天引きされません。
これで会社に副業収入が知られにくくなります。
たとえば、確定申告書や住民税申告書に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選んでおけば、副業分だけ自宅に納付書が届きます。
注意点としては、申告ミスがあると会社に連絡がいく場合もあるので、しっかり書類を確認しましょう。
副業バレを防ぐなら、必ず「普通徴収」を選んで提出しましょう。
会社にバレない副業ブログ運営チェックリスト【50代からの安全ガイド】
この記事はプロモーションが含まれています。A. 住民税でバレない!確定申告と普通徴収の基本 副業が会社にバレる一番の原因は、住民税の通知方法にあります。だからこそ、「確定申告」と「普通徴収」のしくみをしっかり理解しておく […]
医療費控除や住宅ローン控除も併用できる?
- 確定申告では、医療費控除や住宅ローン控除なども同時に申請できます。
副業ブログの所得がある場合でも、他の控除制度と同じタイミングで申告が可能です。
必要な書類や領収書をしっかり用意して、忘れずに一括で申請しましょう。
たとえば、医療費控除は1年分の医療費が一定額を超えたとき、住宅ローン控除はマイホームを購入した年やローン返済中に受けられます。
ブログ副業と組み合わせて申告すれば、より多くの税金を減らすことができます。
せっかくの控除制度は、まとめて活用して節税に役立てましょう。
▼【メルマガ登録案内】
記事をお読みいただき、ありがとうございました。
さらに「50代からのブログ・副業で失敗しないためのコツ」「リアルな成功&失敗談」を、無料メルマガで詳しくお届けしています!
今なら「50代・60代から始めるブログレポート」と、「今日から始める50代・60代、ブログのススメ」レポートを無料配布中です。